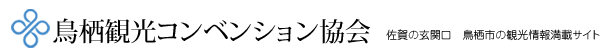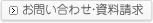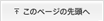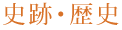
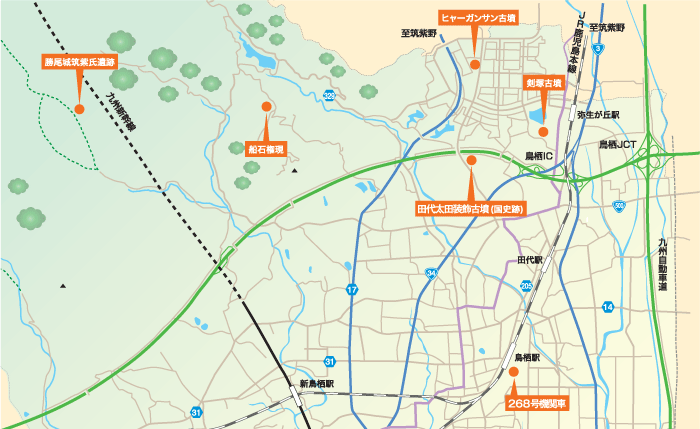
268号機関車

明治38年(1905年)に製造され、昭和10年代(1935~1940年)にかけて運用されていた機関車で、かつて鳥栖の繁栄の要ともなった歴史的文化財です。JR鳥栖駅東に展示されており、誰でも見学することができます。
ヒャーガンサン古墳

1998年に発見された鳥栖市内にある古墳の中でも比較的新しい古墳。現在、弥生が丘の梅坂公園に移築復元されています。直系20mの円墳で、石室内には、装飾文様が描かれており、申込みがあれば、随時公開しています。
勝尾城筑紫氏遺跡(かつのおじょうちくししいせき)

戦国時代後期、鳥栖を本拠に勢力をふるった筑紫氏の本城勝尾城跡。付近一帯に城下町跡が良好な状態で残っています。歴史的価値の高い遺跡として国史跡に指定されました。毎年春と秋の遺跡見学会では、ボランティアガイド「ふるさと元気塾」が案内。一般の見学についても、説明の依頼があれば、対応します。
問い合わせ先……鳥栖市教育委員会生涯学習課
TEL.0942-85-3695
田代太田装飾古墳(国史跡)

柚比遺跡群の南端にあたる田代本町の丘陵上に位置する装飾古墳です。装飾古墳とは彩色画または線刻、浮彫などで石室内などに装飾を施したもので、筑後川、有明海沿岸に多く分布します。田代太田装飾古墳は彩色壁画系の装飾古墳としてははやくから知られていました。6世紀後半代に造られた直径42メートルの大型円墳で、高さ約6メートルの墳丘は二段に築かれています。石室は前室、中室、後室の3部屋からなる全長約9メートルの珍しい構造の横穴式石室が南向きに開口しており、死者を安置する屍床は後室に3体分、中室に2体分設けられています。
舟石権現(ふないしごんげん)

この石造は、東から見ると、帆かけ船が一杯に帆をはらみ、海の上をすべっているかのように見えることから「舟石権現」と呼ばれています。しかし、いつ、誰が、何のために、どのような方法で巨石をくみ上げたのかについては、
(磐座説)神は依代に降りてくる。
(天磐船説)黄泉の国へ島の案内する船で行く。
(郡境石)古代、きい郡、養父郡の境界は大木川か?
(条里指標)石は東西南北を向き条里を決める指標としたなどの諸説がありますが、また定説はありません。
天保4年(1835年)きい養父88カ所の「4番札所・大日如来」が祀られ、現在も参拝も絶えません。
鳥栖市河内町
鳥栖火葬場の前を通り抜け、北西に坂道を登ると異様な石造物が眼に飛び込んできます。